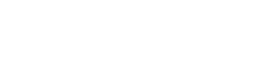④らくがきメソッドの理論とエビデンス
脳科学との関連 ― "描く"が脳を整える
「手を動かす」ことが、脳の整理と再起動を促す。
らくがきメソッドは、手を動かし、色を選び、形を描くという単純な行為の中に、脳を整える仕組みを備えています。これらは感情・思考・身体をつなぐ脳の神経ネットワークを活性化し、情報処理や集中力の回復に深く関わっています。
右脳と左脳の協調を促す
人が描くとき、言語を司る左脳だけでなく、イメージや感情を扱う右脳も同時に働きます。
自由に描くことで、右脳(感性)と左脳(論理)の連携が促され、思考が一方向に偏らず、創造と分析の両面が自然に統合されていきます。
ビジネスの現場で求められる「直感と判断の両立」は、まさにこの脳の協調から生まれます。
報酬系の活性化とストレス軽減
クレヨンや色鉛筆で線を引くとき、脳の中では"報酬系"と呼ばれる神経回路が働き、ドーパミンやセロトニンが分泌されます。
この化学的変化によって、「楽しい」「落ち着く」といった感覚が生まれ、ストレス反応が和らぎます。
感情が安定し、注意力や判断力が戻る――これが、描くことが「脳のセルフケア」と呼ばれる所以です。
- ストレスの軽減と集中力の回復
- 情動の安定とポジティブ感情の増加
- 前頭前野の安定化による思考の明晰化
フロー状態への導入
自由に描いているとき、人は時間の感覚を忘れ、没頭(フロー)の状態に入ります。
このとき脳内では、過剰に働いていた前頭前野の活動が静まり、内省や創造性に関わる"デフォルトモードネットワーク"が活性化します。
考えすぎていた思考がいったんリセットされ、直感的なアイデアが生まれやすくなるのです。
「描く=考えないこと」ではなく、「描く=思考を整えること」。頭を空にする瞬間にこそ、創造の余白が生まれます。
五感を通じて脳を再起動する
クレヨンという素材を使う理由も、科学的根拠に基づいています。
手で握り、摩擦を感じ、色の濃淡を確かめる――この多感覚的な刺激が、脳の運動野や感覚野を活性化します。
身体の感覚と思考が再びつながることで、意識の「分断」が癒やされていきます。
- 触覚刺激による脳活性化
- 運動感覚と感情の再統合
- 身体を通じた自己理解の深化
感覚の知性 ― Science of Sensibility
「自由に描く」とは、自由に"考えない"ことでもあります。
頭を空にしてペンを走らせることで、脳は整理と創造のモードへ切り替わります。
それは感覚と理性のバランスを取り戻す行為であり、現代人に欠けがちな「感覚の知性(Sensory Intelligence)」を育てる時間でもあります。
科学で説明できる"感覚の知性"。
それが、らくがきメソッドが企業研修・教育現場において支持される理由です。
理論的背景 ― ユング心理学を基盤にした"描く思考"のメソッド
描くことで、言葉にならない心の動きを可視化する。
らくがきメソッドの理論的な基盤には、スイスの心理学者カール・G・ユングの「分析心理学」があります。
ユングは、人の心には意識と無意識があり、無意識の中には「集合的無意識」と呼ばれる深層領域があると考えました。
描くという行為は、この無意識にアクセスし、象徴として表出させるアプローチの一つです。
harunでは、ユング心理学の考え方を現代的なビジネスや教育の現場に応用し、
人や組織の「内なる力」を引き出すための方法論として体系化しています。
無意識と象徴へのアプローチ
ユング心理学では、夢やイメージ、絵などに現れる「象徴」は、無意識からのメッセージとされています。
言葉では説明できない感情や価値観が、形や色として自然に表れ、
描いた本人にとって"今の自分"を映す鏡となります。
描かれた図形や線、色の組み合わせには、本人も気づいていない思考のパターンや感情の流れが現れます。
それを見つめ直すことで、思考と感情のズレを整えることができるのです。
アクティブ・イマジネーションと自己統合
ユングが提唱した「アクティブ・イマジネーション(能動的想像法)」とは、
意識と無意識の対話を促す創造的なプロセスです。
描くことはまさにこの実践であり、
無意識のイメージを意識のレベルに引き上げ、対話する行為と言えます。
この過程で、抑え込まれていた感情や未整理の思考が統合され、
自己理解が深まり、行動の一貫性が生まれます。
組織においても、メンバー一人ひとりの価値観が可視化されることで、
互いの多様性を尊重し合う土壌が育まれます。
- 描く=内面との対話を生む
- 意識と無意識の統合を促す
- 多様な価値観を認め合う文化をつくる
組織における統合と共感
個人の内面が整うと、チームの中でのコミュニケーションにも変化が起こります。
「描く→共有する→感じる→気づく」というサイクルを通して、
メンバー同士が互いの考えや感情を尊重し、
共通の理念を"自分ごと"として理解できるようになります。
理念やビジョンが"経営者の言葉"ではなく、"組織全体の物語"へと変わる。
それが、らくがきメソッドが組織に提供する最も大きな価値です。
描く思考がもたらす統合の力
らくがきメソッドは、ユング心理学における「自己統合」のプロセスを、
現代の組織開発に応用した手法です。
一人ひとりの心が整うことで、チームが整い、組織が整う。
この「内側からの変化」を大切にしています。
描くことは単なる表現ではなく、意識の深い層に触れる"行動する心理学"。
だからこそ、研修や教育現場での実践が長期的な変化を生むのです。