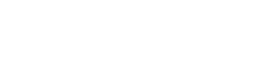①らくがきメソッドとは
らくがきメソッドとは
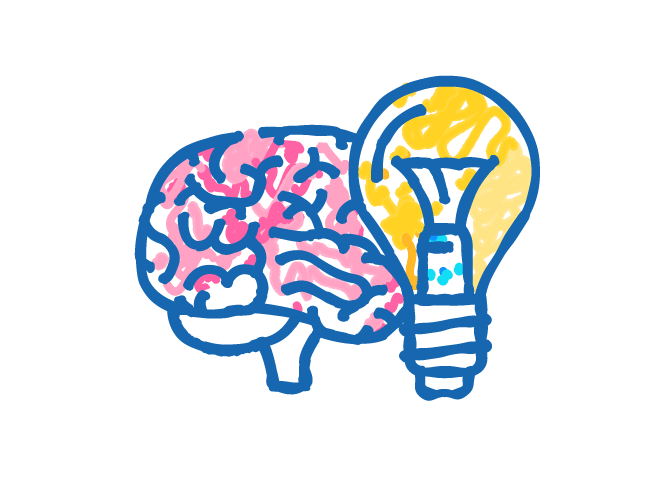 描くことで"無意識の声"を可視化し、思考と感情を整える。
描くことで"無意識の声"を可視化し、思考と感情を整える。
「らくがきメソッド」は、描くというシンプルな行為を通じて、思考や感情の奥にある"無意識の声"を可視化する体感型メソッドです。
アートセラピーの理論を基盤に、心理学や脳科学の知見を取り入れて体系化されました。
無意識の領域には、言葉にできない感情や価値観、潜在的な思考パターンが存在します。
それを"描く"ことで表に出すと、頭の中に散らばっていた情報が整理され、物事の優先順位や本質的な課題が見えやすくなります。
結果として、コミュニケーションのズレが減り、チーム内の共通認識が深まるなど、意思決定の質が自然に高まっていきます。
描く行為がもたらす「整理と気づき」
人は思考を言語化しようとするとき、左脳(論理)を使います。
一方で、感情や直感は右脳の領域にあり、言葉ではうまく表現できません。
「描く」という行為は、この右脳と左脳の橋渡しをします。
ペンやクレヨンを手に取り、自由に線を引くことで、思考の流れが目に見える形となり、頭の中が整理されていきます。
そのプロセスの中で、言葉では掴めなかった"自分の本音"や"組織の課題"が自然に浮かび上がります。
描くことで得られるのは分析ではなく「気づき」。考えすぎていた頭が少し緩み、内側に眠っていた直感が立ち上がる。その瞬間に創造的な発想が生まれます。
脳科学に基づいた「右脳と左脳の統合」
脳科学の視点から見ると、"描く"という行為は、右脳と左脳の連携を促す働きを持っています。
右脳が感覚的なイメージや感情を生み出し、左脳がそれを言語や構造に変換する。
この往復運動が、思考をより立体的にし、創造力と論理性をバランスよく引き出します。
また、描くことは脳内の"報酬系"を刺激し、ドーパミンやセロトニンなどの神経伝達物質の分泌を促進します。
これにより、ストレスが和らぎ、集中力とリラックスが同時に得られる状態になります。
- 創造性を高めたい組織に有効
- 集中力・ストレス耐性の向上
- チームの共感力を育てる
組織の中で起こる変化
らくがきメソッドを取り入れた研修では、参加者が描いた"個々の内面"がチーム全体の"対話の起点"になります。
絵をきっかけに感情や価値観が共有されると、互いの理解が深まり、心理的安全性のある関係が生まれます。
理念やビジョンも、単なる言葉ではなく"共感"を通じて実感されるようになります。
これにより、社員が自ら動き出す"自走する組織文化"が育ち、研修で得た気づきが行動として定着していくのです。
描くことは「考えること」よりも深い
らくがきメソッドは、分析や理屈ではなく、体感を通じた気づきのデザインです。
描くことで思考が整理され、心が整う。
個人の変化が、やがて組織全体の変化へとつながります。
「描く」という原始的で創造的な行為が、現代のビジネスやチームづくりにおける"最も人間的な学びのかたち"として再評価されています。